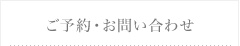子どもの矯正について
子どもの矯正を始めるタイミングが大切です
歯並びや噛み合わせが悪いと、お口の中の環境が悪くなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、口元を隠したり、人前で話すことが苦手になるなど心の成長に悪い影響を及ぼすことがあります。

また、歯並びや骨格、あるいは成長スピードによって、早期治療が適している場合があれば、成長を待ってから始めた方がよい場合もあります。治療を始めるタイミングが大切ですから、気になったら早めにご相談ください。
できるだけ取り外しできる矯正装置をお勧めしています
お子さまの場合、歯磨きがきちんとできないと虫歯になりやすく、また成長の途上でもあるので、治療後の安定を重視すると、できるだけ取り外しできる矯正装置をお勧めしています。固定式の装置による治療はなるべく後の方がよいと考えています。

早期治療が必要な場合は、年長さんの頃から
あごが成長する前に治療が必要な場合や、舌足らずなど舌機能の訓練が必要なケースは、治療のタイミングを逃してしまうと骨格にズレが生じます。さらに成長してからでは治療が難しくなり、治療期間もそれだけ長引きます。
早期治療の必要のないお子さまは、経過観察
適切な時期を見極めるためにも、歯並びが気になる場合は永久歯の前歯と奥歯が生えてくる6~7歳頃に矯正歯科を専門に行う歯科医師の診断を受けると安心です。当院では、ご相談を実施しており、早期の矯正治療が必要ないお子さまの場合は成長を見守らせていただきます。
小さいお子さまも、本人の意思を尊重します

一番大切なのは、お子さまご自身の気持ち
矯正治療は、お子さまご自身が自分でも治したいと思って治療に前向きになることが大切です。お子さまご自身に治す意思があれば、装置をきちんと付けて治療が順調に進みます。当院では、小さいお子さまにも「矯正治療をする?」と本人の意志を確かめてから治療に進みます。
治療を嫌がるお子さまは、クリーニングから
嫌だなと思っているお子さまや、治療したいと感じていないお子さまには、治療を見合わせます。「春休み・冬休み・夏休みに先生のことを思い出してね」とクリーニングに通ってもらい、お口の中の成長やお子さまの気持ちに合わせて、治療開始のタイミングを図ります。
小児矯正の流れは、大きく分けて2ステップ

子どもの矯正治療は、お子さまの成長に合わせながら2つのステップに分けて治療を行います。第一期治療が終わったら、しばらく治療を休み、永久歯が生えそろってから第二期治療を始めます。
第一期治療(小学校3、4年くらい)
◎期間:約2年
成長と共に歯並びや噛み合わせを悪化させる要因を取り除き、その後の発育ができるだけ正常に近づくための治療を行います。この段階の治療がうまくいくと、第2期治療をせずに済むことがあります。また第2期治療に移行したときに負担が少なく、永久歯を抜かずに矯正できる可能性が高まります。
第二期治療(自分で意識的に管理ができる年齢が目安)
◎期間:約2年
噛み合わせを正しくすることを目的とし、大人の治療と同様、歯にブラケットを装着して治療を行います。初診時に永久歯が生えそろっている方は第2期治療から始めます。
小児矯正で使用する装置をご紹介します

歯列拡大装置
一週間に1~2回ネジを回すことにより、左右の奥歯を支えにして上顎骨を拡大する装置です。(取り外し式)

歯列矯正用咬合誘導装置(ムーシールド)
低年齢の受け口(成長期反対咬合)の治療では、マウスピース型の歯列矯正用咬合誘導装置(ムーシールド)を使用します。就寝時のみの使用で治療効果を上げられるので、反対咬合は永久歯が生えるまで待つことなく、3歳児からの治療が可能になりました。
機能的顎矯正装置(F.K.O・アクチベーターアクチバトール)
主に成長期の患者さま自身の咀嚼筋の力によって歯を動かしたり、あごの成長をコントロールして、骨格性の問題を解消する装置です。成人の患者さまでも一部噛み合わせの深さのコントロールなどのために使用する場合があります。(取り外し式で、主に就寝時に使用)
バイオネーター
主に成長期の患者さま自身の咀嚼筋の力で歯を動かし、歯列を広げたり、顎の成長をコントロールして、骨格性の問題を解消する装置です。歯列を拡大する効果もあります。(取り外し式で、主に就寝時に使用)

緩徐拡大装置(クワドヘリックス)
歯の裏側の針金を調節することにより、比較的ゆっくり歯列を拡大する装置。装着期間は6ヶ月~1年程度で成長期の患者さまだけでなく、成人の患者さまにも使用できます(固定式)

タングガード付矯正装置
つばを飲み込むときや話すときに舌を突き出す癖があると、不正咬合や矯正治療後の戻りの原因になる場合があります。タングガードは、舌の前方への移動を防止するワイヤーです。
矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用
●治療期間
治療期間は1ヶ月に1~2回の来院を原則に、永久歯の矯正治療で2~3年程度です。歯の萌出や歯の動きには個人差がありますので、計画した期間が多少変更されることがあります。また治療の難しい症例ほど治療期間もかかります。最も期間を要するものには、著しい反対咬合、開咬、舌や噛み方に著しく間違った習慣がついている場合などが挙げられます。
●矯正装置の装着・撤去時
通常の治療時間は30分位ですが、装置の装着・撤去時は約1時間くらい必要です。
●食後の歯磨きをおろそかにすると
矯正治療中は食べ物が詰まりやすく掃除が難しくなります。毎食後の歯磨きは必ず行ってください。私たちスタッフも歯磨き指導を中心にできる限り予防処置を行います。
歯磨きをおろそかにすると歯の表面が溶け、虫歯や歯ぐきの炎症が起こります。これらの程度が進行しますと、治療が続けることができなくなり、装置を外すこともあります。
●治療の成果
治療を成功させるためには、患者さん自身の努力やご家族、周囲の人達の協力が必要です。装置を十分に使用しない、予約を守らない方の場合は治療がうまく進行せず、治療期間が延びるだけでなく、治療結果が不十分になることがあります。取り外し式装置やアライナー矯正装置(マウスピースタイプ)は約20時間/日の装着が必要です。治療上必要な事項を守れない場合は、治療の継続をお断りすることがあります。
●矯正治療中の痛み
矯正装置が装着されると、始めの頃は頬の粘膜を咬んだり、口内炎ができることや、装置の種類により喋りにくい場合もありますが装置に慣れるにしたがいこのようなこともなくなります。また、ワイヤーを調節してから3~4日位は個人差がありますが歯が浮いたような感じになり、食事の時などに痛くなることがあります。この間、必要なら柔らかい食事をとり、食後は優しくマッサージするように歯磨きしてください。もしどうしても痛みが強い場合は「バファリン」など、ご自分に合った鎮痛剤を飲んでも結構です。一般的には日常生活に支障のあるほどの痛みではありません。
●治療の途中で…
治療の途中で、歯が一時的に「噛みにくい」「出っ歯になる」「受け口」「隙間が出る」など患者さんが不安に感じるようなことが起こることがあります。これらは、治療のゴールに向かう一行程にやむを得ず発現するものです。どうぞご心配せずに指示に従って通院してください。必ず改善しきれいになります。
●「針金が飛び出した」「装置がぐらぐら! 」など…
ときどき治療中の装置から針金が飛び出したり、装置が外れてグラグラしていることがあり、びっくりすることがあるかもしれません。原因はいろいろ考えられますが、まず割り箸等で押し当てて中に入るのもあります。しかし、ワイヤーが歯ぐきや粘膜を傷つけて痛い時は早めにご連絡ください。うまくいって、気にならないようであれば次回までそのままで結構です。
●治療計画の変更
治療計画は患者さんごとに異なります。治療の途中で、装置の使用状況、著しい骨格 性変化、舌の突出癖や歯の動きなどによる予測できない事柄で、治療期間の延長、治療計画、治療方法の変更、抜歯などが必要になる場合があります。
●歯肉(歯茎)の後退、歯根の吸収
歯が動く時、歯茎が後退(ブラックトライアングル)や個人差がありますが、歯の根の先が吸収し短くなることがあります。多くの場合日常生活での支障はありません。そのような症状が認められた場合、個別で対応いたします。
●現代人のあごの関節はとても弱くなっています
ごの関節から音がしたり、開けにくくなったり、痛みを感じる人が増えてきています。矯正治療はこういった現象の直接の原因にならないと言われていますが、治療中このような症状が起きたらお知らせください。お口を安静に保ち、固い食物や大きく口を開けるなどあごに負担がかかることはなるべく行わないように注意してください。
●受け口(反対咬合)の人などでは
成長期の場合、治療中・治療後に下顎が著しく成長することがあり、矯正治療だけでは十分な対応ができにくくなることがあります。このような場合は矯正治療と併用して外科手術が必要になることがあります。
●後戻り、再発と再治療
矯正治療が終わるときれいな歯並びを維持するため「保定」は、とても大切です。装置を外したあと、しばらくの間歯が元の位置に戻ろうとする現象が起こりますので、必ず保定装置を使用してこれを防止します。保定装置には取り外しができるタイプや、歯の裏側に目立たないように接着するタイプなどがあります。一般的に保定装置は、歯が新しい環境に慣れるよう最初の6ヶ月間は食事や歯磨きなどの時を除いて一日中使用していただきます。その後、経過により夜間のみ使用など指示いたします。保定期間は通常2年間くらいですが、その間3ヶ月に1回来院してください。お口の中を拝見し、装置を調整します。保定装置の使用協力が不十分で再治療が必要になった際には、再治療費として治療費の一部が別途必要になります。
●親知らず(第3大臼歯)の抜歯
親知らずのある人で生えてくるスペースがなく(存在しているが埋まっている場合が多い)、その萌出力によって再び矯正治療後の歯並びやかみ合わせに悪影響を及ぼすおそれがある場合や、萌出しているがかみ合う歯がない、衛生管理できないと判断された場合は治療前・後に抜歯が必要です。
●加齢にともなう歯並びの変化
年齢が増えるにつれて、生理的に歯の「乱ぐい」や「歯間のすき間」ができることがあります。これは生理的老化現象の一つで、年を取れば誰にでも発生するものです。矯正治療とは直接関係ありません。しかし保定装置を使用し、管理を続けることにより歯並びを長期に維持することはできます。